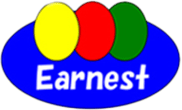風の時代を読む研究会
2025.02.21 風の時代を読む研究会(第3回)
多極化に向かう世界において建設的な役割を果たす
ー下斗米名誉教授からロシアの戦略を学ぶー
令和7年2月21日、第3回目となる「風の時代を読む」研究会を下斗米伸夫神奈川大学特別招聘教授・法政大学名誉教授を迎え、『プーチン政治二五年とウクライナ和平』と題する講演を聴いた。ロシアとの出会い、プーチン大統領バルダイ会議、米国問題としてのウクライナ戦争、11月のロシア訪問の最新情報などが話された。(注1、注2)

講師の下斗米伸夫先生「バイデン前大統領の息子のハンターは、ウクライナ・ロビイストである。正直言って民主党の政治家はお金にきれいではない」「そういう意味でトランプ共和党の方がロシア人たちも安全保障等で交渉できる」という。研究会、活発な意見交換がされた。前後するが左から小平和一朗、下斗米秀之、森下(座長)、下斗米講師、西河洋一、長谷川一英、吉池富士夫。
講 師:下斗米伸夫(神奈川大学特別招聘教授・法政大学名誉教授)
参加者:森下あや子(座長、日本経済大学大学院教授)、
西河洋一理事長、
吉池富士夫(芝浦工業大学理事)、
長谷川一英(E&K Associates代表)、
下斗米秀之(明治大学経済学部専任准教授)
小平和一朗専務理事、
松井美樹(事務局・理事)
5年ぶりモスクワに行ってきた
座長の森下あや子は「下斗米伸夫先生お越し頂きありがとうございます。ホットなロシアに11月に行ってプーチンに会われたということでお聞きすること楽しみにしております」と講師を紹介した。

「アメリカの富の半分位をIT長者とかオリガニヒが支配している」と下斗米伸夫名誉教授
【下斗米伸夫氏の講演から】
色々な人と話をするが、2019年以来、24年10月末モスクワを訪れた。街の雰囲気も戦時下とは思えず、戦時ポスターやスローガンも多くはない。今回の訪問時、武藤大使らは首相からの信任状をプーチンに提出した。プーチンは、日本に対立は求めなかった。
モスクワ大学で日本の政治について講演した後、ソチでプーチン大統領を囲む会があった。日本人が呼ばれたのは、日本についての関心をずっと持ち続けているということだと私は理解している。
11月7日プーチン・バルダイ会議
バルダイ会議に15年位付き合っている。基本的に西側50人位との交流の場だった。今は中国、インド、インドネシア、イランなどの会議体である。英米は少なくなった感じがする。プーチンの会議での発言を次に紹介したい。
「世界は西側諸国の覇権から多極化へと向う」「新しい世界秩序は、多様性、協力、相互尊重に基づくべき」「ロシアは、西側諸国とは異なり、対立ではなく協力を重視」「BRICSは新しい世界秩序のモデルとなる可能性を秘めている」「国際社会は気候変動、貧困、不平等などの課題に共同で取り組む必要がある」「ロシアは自国の主権と安全保障を守るとともに、多極化に向かう世界において建設的な役割を果たす」。
バルダイ会議へのコメント
昨年秋と比べてもプーチンは世界政治と経済への対応で自信を持ったとの印象であった。プーチンは、報告の1時間を含め4時間しゃべった。メモも見ない。
10月のロシアにおけるBRICS諸国会議で参加した国の世界人口に占める割合は四割以上。またトルコ、インドネシア、タイ、ベトナム、スタン国などが参加。G20首脳会談でもウクライナ戦争のロシアへの理解が広まっている。
米英がプーチン打倒を迫り長期化
プーチンはウクライナ侵攻を3日で終わらせる計画で22年2月14日に開始した。「特別軍事作戦」、10万余の作戦、キーウ占領が目的ではなかった。しかし国連憲章違反のプーチン戦争となった。24年11月20日で千日と長期化した。侵攻の目的はウクライナの「非軍事化」「非ナチ化」「独立以来の中立化」だった。
ゼレンスキーは、直後ロシアとの中立化交渉に応じ22年3月29日にトルコの仲介でイスタンブール合意停戦と領土問題の凍結で合意しかけていた。しかし米国のバイデン大統領、特に英国のジョンソン首相の強硬姿勢がキーウに武器提供をする代わりにロシアの弱体化・プーチンの打倒を迫り、西側の介入で紛争の長期化を招いた。
三つの複合紛争
- 二つのウクライナ、ウクライナ内部の対立が内戦へ(14年~)
- ウクライナとロシアとの戦争(22年2月~)
- NATOとロシアとの代理戦争(22年4月~)
という3つの性格の異なる戦争が同時進行。ウクライナ内部で東西間の文明の衝突が起きている。
経済制裁が強めたロシア軍需経済
- 西側諸国が実施したロシアへの経済制裁は意図とは逆にロシア経済を強化する結果となった。
- 制裁により海外に逃れていたオリガルヒが富とともにロシアに帰国し国内投資が促進された。
- 輸入代替効果により農業などが成長し、BRICS諸国との経済関係も強化された。
英国は巨大なパワーまずいと分断
イギリス外交からすればユーラシア大陸に一つの巨大なパワーがあるのはまずい。中国とロシアを分断し、ドイツとかフランスを分断する戦略をとる。
イギリスがこの5百年間やってきた地政学。ナポレオンやヒトラーは許さないという哲学。
これに対しフランスとドイツが少しずつ違った理由でヨーロッパの王者はどっちかと。今ドイツ経済は相当左前だ。安いロシアのエネルギーが入ってこない。フランスは移民問題ということで。その意味では世界が1945年に作られたメカニズムとは別のメカニズムになろうとしている。
もう戦う兵士がいない、弾薬がない
この紛争もう戦うウクライナ兵士がいない。金をいくら注ぎ込んでも兵士は作れない。大量の砲弾を撃ち合うということが、戦争の基本的なパターンになるとは誰も考えてなかった。従って弾薬はもうない。
非常に奇妙な戦争をどうやって終わらせるかが、今年の重要な課題。
宗教あればお金あり
ニューヨークの中にもユダヤ人がいるし、イスラエルに今一千万人いるが超イスラエルを作った人たちはオデッサ周辺の宗教的シオニストというグループで、元々ソ連共産党の前のユダヤ系労働党グループというのは、同じ集団農地を作ったりした共産党と根っこが繋がっている。
ウクライナ戦争にも見え隠れする共和党系と民主党系のユダヤ人の金儲け。だからソロス財団というのが民主党のユダヤ・ロビー。バイデンが辞めるときにハンガリーのジョージ・ソロスという有名な投資家に勲章を与えた。彼がNATO拡大に献金した。ウクライナ戦争にはその金が相当入っている。
トランプ政権になって3千5百億ドル使っている金はアメリカが払ったからレアメタルで返せと言う。宗教あればお金あり、お金あればそれを守る権力、裏と表の権力あり、それが三位一体にぐるぐる回る。世界史というのはそういうものだ。
(注1)下斗米伸夫(2022)『プーチン戦争の論理』インターナショナル新書
(注2)下斗米伸夫(2020)『新危機の20年』朝日新聞出版
質疑応答
森下(座長):質問とかご意見あればお願いします。
日本のガスプロムはなぜ止まらない
(西河):プーチンには日本の意見を聞きたいので招かれたのか。実際僕もプーチンと会って話をしているし、例えば日本が制裁を今回かけているが普通であればガスプロムは止まるはず。なんで動いているか。その辺が理解できない。
講師(下斗米伸夫):今回日本政府は経産省を中心にいろんなネットワークを使い「サハリンのガスを止めてくれるな」と活動している。
(西河):都合がいいように片方にはこう言ってその理屈がわかない。プーチンはちゃんと日本のことを考えてくれている。武道をする人だし礼儀も正しい人だ。広島に来て十字架も切ってくれた。オバマ大統領は来ても何もやらない。
(講師):そうですね。一番最初に東シベリアの天然ガスの利権、財閥の意見がわかれて中国が中国の大慶まで持ってこようとした。それは安全保障の問題になると東シベリアが全部中国に買い占められるとまずいと言って森元首相が話をしてバイカル湖のこちら側を通したのが国営のパイプライン。
パイプラインをナホトカ辺りまで繋げるという構想で北極海をどうしようかということもあった。プーチンがアジアで中国と日本とをうまく競わせ、よく言えばそういう戦略を持っていた。今はこれだけ中露関係が改善しているが。
ロシアは逆に焼け太りで4%成長
経済制裁、ロシア側は最初から見越していた。インドや中国や、イランも北朝鮮も、経済制裁、金融制裁でドルを使わせないからといって色々な抜け道がある。それをやったらむしろロシアは逆に焼け太りで4%成長した。
西側がインフルで苦しんでいるのに、ロシアも今はインフレで物価は上がっているが、軍事的ケインズ主義というなかで経済成長も同時にしている。
米国とロシアで戦争をしている
(小平):ウクライナ戦争を終わらせるのに、米国とロシアだけで話が進んでというのは、ウクライナが統治能力を失っているというのが前提にあると考えていいのか。
(講師):事実上、ゼレンスキー政権は、アメリカが支援する金で作った政権である。戦争するには大体ひと月60億ドルかかる。アメリカ、EU、日本で分担している。
(小平):資金出しているから、引いたら停戦するということか。
(講師):そういうことになる。
ソ連は東部4州が欲しかった
(吉池):当初は、4州でなく全部欲しかったのではないか。
(講師):いいえ、私の見方は最初から東部4州である。ミンスク合意はあそこに自治権を与える。4州ではなく2州に自治権を与えて住民投票をやるというのがゼレンスキーが和平派で出てきたとき、クリミアは別であるが、提案したのはゼレンスキーだった。
ところがゼレンスキーは、モスグリーン派、テロ集団にやられかけて、それで変えた。多分プーチンは250万の都市を攻撃するとしたら数十万の兵士を出さなければいけなかったはずがキーウを攻撃した時、10万人である。
その後、イギリスの首相が乗り込んできて、武器は好きなだけ提供すると言ってバイデンもプーチン体制を壊さないと駄目だと言ったので長期戦に入った。