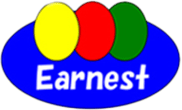風の時代を読む研究会
2024.05.30 風の時代を読む研究会(第1回)
教育を怠り現場力はどこに
海外人材を育成し米国は経済成長
令和6年5月30日、風の時代を読む研究会を財団内会議室にて開催した。「風の時代」といわれる変革の時代を読み取り、変革の嵐に耐えられる企業経営を研究し、その知見を経営者に教示できるように整理。下斗米秀之専任講師が『米印関係史に学ぶ人材育成』と題し講演した。

講 師:下斗米秀之(明治大学政治経済学部専任講師)
参加者:森下あや子(座長、日本経済大学大学院教授)、
西河洋一理事長、
小平和一朗専務理事、
吉池富士夫(芝浦工業大学理事)、
長谷川一英(E&K Associates代表)
「米印関係史に学ぶ人材育成」と題し、風の時代を読む研究会
—海外と比較して日本は元気がない—
財団は中小企業の経営者に狙いを定めた経営人財の育成に取り組んでいる。変革の時こそ中小企業が躍進する好機だ。4月の研究会準備会合で森下座長より海外と比較して日本は元気がないと問題提起。その原因を探るべく、下斗米明治大学専任講師を招き米印の動向の講演を依頼した。
超大国アメリカが、どう人材を育成し供給し経済成長に繋げたか
経済史の中でもアメリカの移民問題、この歴史と現状というところに関心を持っており、その中で具体的には移民を通じて、あるいは留学生を通じて、様々な技術の移転が国境を越えて起きていると考えている。
頭脳流出とか、頭脳循環という問題と深い関わり合いを持っている。人の移動を通じたアメリカ経済が研究のメイン。『アメリカ経済史に学ぶ』と題する本紙への連載は時事問題やアメリカ研究の本を読んでコメントするとともに『米国経済白書』(注1)も紹介。
本日は、科学技術の分野の人材供給が重要で、超大国アメリカを作り出してきたかを話す。どのように人材を育成、供給し、経済成長に繋げてきたか。注目しているのがアジアからの高度人材の利用で、国内における人材育成と国外からの即戦力の流入という二つが冷戦期以降のアメリカの科学技術覇権を確立させた。
インドが高度人材の重要な供給源
インドがアメリカの高度人材の供給源になっている。中心にインド工科大学(IIT)がある。IITはインドのMITと言われるが、欧米各国が大学設立の支援をしている。その背景に冷戦下の競争が熾烈だったことがある。
アメリカはソ連に西側の盟主として東側に大きな顔をさせたくなかった。ソ連が原爆の実験に成功し、人工衛星スプートニクスを飛ばされたのはショックであった。それは科学技術が戦後世界の覇権にとって極めて重要であるとの認識があった。危機に対してリソースをかけて一気に対応した。
(注1)萩原伸次郎監修、萩原伸次郎、大橋陽、下斗米秀之訳(2023.10)『米国経済白書2023』蒼天社出版
米国は国防教育法を作る
1957年のスプートニクショックの翌年、連邦政府が科学技術政策の統制強化を進め国防教育法という法律を作る。高度人材の育成が国家的プロジェクトとして浮上。科学技術や数学、外国語、その他の学問領域で学生を増やし国防に取り組む。科学技術の領域で優位を獲得する狙いがあった。
同法によってアメリカは科学技術者が育成されて科学覇権を握ることができたと見られているがそこまで単純な話ではなく50~60年代の労働統計局の資料を見ると科学技術者は不足しており、60年代以降には人材不足がさらに激化する予測が立てられた。
人材育成には時間がかかるのでソ連の脅威とか冷戦の激化を念頭に楽観的でいられない。科学とか工学の学士号を持つ新卒者はもちろん、大卒でなくても技術職ついている人たちや退職したエンジニアを連れ戻す程の人手不足で当然移民を考慮しなければいけないという議論もされた。国家安全保障に関わるような理工科系人材を国ぐるみで作る必要があった。
民間の財団がインドに対し支援
フォード財団やロックフェラー財団などの民間財団はインドに対し支援した。学校の設立や色々な奨学金を出して多くの優秀な人材を受け入れた。産業界も連携し鉄鋼業等、独立後のインドの経済成長に重要な鉄鋼業界をUSスチールやベスレヘムなどが支援した。実地研修や工科大学でのスクーリング、週末のプライベートな交流を通じて将来の米印関係を担う人材を積極的にアメリカが支援し、育成した。ソ連やイギリスも同様で技術援助の舞台となった。
米国へ頭脳流出が大きなテーマ
インドは自立的な工業化を成し遂げたが、皮肉なことに育成された人材のスキルを活かす仕事がインドには多くなかった。多くのエリート層が自分のキャリアを活かすため、もっと勉強をしてスキルを上げたい理由からアメリカに行き頭脳流出と呼ばれる。国際的な移動の流れが冷戦という文脈の中で作られた。
IITは欧米諸国の援助で出来た
MITがカリキュラムを提供したり、フォード財団が資金提供をしたり国がサポートする産官学連携展開しIITができた。ソ連がつくるボンベイ校とか西ドイツが作るマドラス校とかイギリスが作るデリー校とか各国も大学を作った。
内部留保、日本は投資をおこたった
一人当たりのGDPや賃金の伸び率で深刻な状況にある。理由はさまざまでICTへの過少投資などの技術的なことはもちろん人口動態を見ると楽観的でいられない。
高齢者の増加や労働生産性の低下なども問題で高齢者介護などが課題となっている。出生率の低迷も日本やアメリカのみならず先進国全般の課題である。海外からの移民を入れる議論がある。日本の場合、非熟練労働者は給料が低いから受け入れている側面が大きくあまり良くない。
移民との共生に向けての取り組み
既に日本は事実上の「移民大国」になっている。共生に向けての取り組みは喫緊の課題である。日本の治安の良さや住みやすさ等、生活の安定性を高く評価する声もある。賃金が低いといっても母国より稼げる人が多くネガティブな側面だけではない。アメリカではアジアンヘイトもあるし、生活コストの高騰、インフレの影響を受けているので日本はソフトパワーの部分を強調すべき。
チャレンジができない体質を改善
日本の企業の問題は様々であるが内部留保の多さや、チャレンジができない体質の改善が必要である。人材への投資等は重要だと感じている。
非正規雇用を増やしてしまった
国際競争力を維持するためにコストカットをしてきたのが日本並びに先進諸国の80年代以降の大きなトレンドだった。日本は非正規雇用を増やしてしまった。非正規労働をたくさん増やすと賃金を上げにくかったり、OJT(注2)等の人材トレーニングを減らした。
アメリカはピンチはチャンスに
アメリカはピンチをチャンスに変えてきた国であり、そこから学ぶ点は大きい。人材育成は、産官学連携の協力体制で取り組む必要があり、いろんなアクターが協力しながら我慢強く粘り強く長くやっていかなければいけない。
技術移転を通じて国際的な人材流動性を高めることも大切で、IITカンプール校の育成は、最初から頭脳流出を狙ったかどうかは分からないが、それが結果的にアメリカを利することになったというのは大きな学びである。
異国であれ、どこであれ、早めに色々な投資をして人材育成をして、こういう人たちが最後に母国に還元していく循環は必要だ。
(注2)OJT: On the Job Training(企業内教育の一つである。職場の上司が、仕事をやりながら部下に対して、必要な知識、技術、技能、マナーなどを「意図的」「計画的」「継続的」に指導し、修得させることで、業務処理能力の向上を計る教育のことである。

「日本はOJT等の人材トレーニングも減らした」と語る下斗米氏

「アメリカの人口ピラミッドは釣鐘状になっていて、生産者人口は永遠に減らない」と語る森下座長、左より西河理事長、森下座長
質疑応答
森下(座長):質問とかコメントとかあれば。
(座長):スカラシップをやっていたと聞いたがどこが払うのか。
下斗米(講師):民間財団が負担していることも多い。大学を作るハード面もソフトの面での人材の育成も含んでいる。
(吉池):超大国アメリカを作るにはどうしたらいいかという答えは人材の育成と人材の流入だと。
(講師):そもそもアメリカは移民の国で経済成長の背後にそうした人材の受け入れがが大切だと思っている。冷戦期をみても、なぜアメリカはこんなに強かったんだろうかと考えていく中で、人材育成や人材供給の重要性を知る。
(小平):インドの人たちは今シリコンバレーで活躍している。今度はその人たちがインドに戻って先進企業を立ち上げるのではないか。
(講師):IITのキャリアパスを見ると、かってはアメリカに行くのがファーストオプションだったが、今のインド人の卒業生たちのファーストオプションがインドに残るということになっている。すでにいろいろな企業が立ち上がっているので、わざわざアメリカに行く必要がなくなっている。
(長谷川):確かトリプルエースとアメリカの科学のミーティングで、チェアーの人が言っていた。アメリカ国籍でノーベル賞を取った人のかなりの部分が移民か、移民2世だと言う。
(講師):確か半分近い。国際労働力移動でいうと、留学生であれ、移民であれ、一時滞在者であれ、結局彼らに永住権を与えて住んでくれればよい。
(座長):楽しい時間を提供していただき、ありがとうございました。