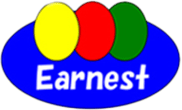風の時代を読む研究会
2024.12.6 風の時代を読む研究会(第2回)
日本には経済政策がない
「インフレ対応で後手になってしまった」
ーハリスはなぜトランプに敗れたのかー
令和6年12月6日、第2回目となる「風の時代を読む」研究会を萩原伸次郎横浜国立大学名誉教授を迎え開催した。研究会では『ハリスはなぜトランプに敗れたのか』と題してアメリカの最新情報を伺った。①ハリスはなぜトランプに勝てなかったのか、②バイデン大統領が不人気だったのはなぜか、③画餅に帰したバイデン・ハリス政権の経済政策の意味するもの、④短期決戦では効果のあったトランプ政権の経済政策の課題について講演された。
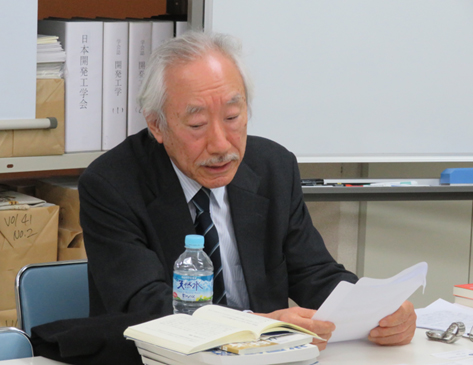
失われた30年、講師の萩原伸次郎横浜国立大学名誉教授は「経済成長率を高めるためには、政府がきちんとした機能を果たさなくてはならない」という
講 師:萩原伸次郎(横浜国立大学 名誉教授)
参加者:森下あや子(座長、日本経済大学大学院教授)、
西河洋一理事長、
下斗米秀之(明治大学経済経済学部准教授)、
吉池富士夫(芝浦工業大学理事)、
長谷川一英(E&K Associates代表)、
小平和一朗専務理事、
松井美樹(事務局)
海外と比較して日本は元気がない
座長の森下あや子は今日は萩原伸次郎先生をお迎えし「ハリスはなぜトランプに敗れたのか」というアメリカ大統領選の話題についてお話し頂くと講師を紹介した。
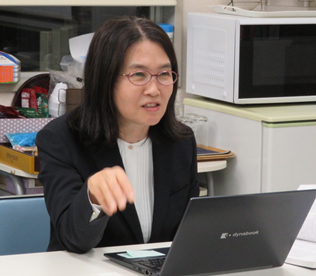
「新しい資本主義の真実」(注1)という萩原先生の著書を読ませていただき是非ということで講師をお願いしました」と森下座長
【萩原氏の講演から】(注2)
要因にイスラエルとハマスの戦争
トランプ勝利の要因の一つはイスラエルとハマスの戦争である。バイデン政権はイスラエル支持である。ユダヤ人ロビーからお金を貰っているので戦争をやめさせようとしない。
ハリスは民主党の大会でガザの状況を見て「パレスチナ人の独立自立を、私は戦争を終わらせる」と明確に言った。しかしその後もイスラエルのガザ攻撃が続く。それをバイデン政権はサポートすることで人心が離れていったことが大きいと見ている。
2回も下院で弾劾訴追をやった大統領が返り咲くというのは前代未聞である。アメリカ史上起こったことはない。なぜ起こったか、決定的なのはバイデン・ハリス政権の経済政策だと見ている。経済政策がアメリカ国民の支持を得られないことが大きな要因だ。
負けていないと4年間言い続けた
21年からバイデン政権が始まるが、トランプは「俺は負けていない」「不正があったから負けたように見えるけど実は俺が勝っている」と言って大統領就任式には出なかった。「俺は負けてない」と4年間言い続けた。タイミングと同時に執念が非常に重要であることを今回の大統領選挙で思った。
減税と規制緩和をやれば良くなる
後から考えるとトランプ政権がバイデン・ハリスよりまだマシかとアメリカ国民を思わせたのは2017年から19年の3年間。つまりコロナが来る前の状況の中でアメリカ経済は着実に経済成長した。
17年の12月に減税と雇用法。トランプ政権は新自由主義である。減税と規制緩和をやれば世の中は良くなるということで17年には、所得税減税。これは一律減税で、レーガン政権以来の富裕層優遇の減税であり、それを実行する。中小の銀行などの規制を緩和してきた。規制緩和の影響がどこで出たかというとバイデン政権のときにシグネチャ銀行などがビットコインの関係で潰れた。元はといえばトランプ政権である。大銀行の規制と同時に規制を外した悪い影響は全部トランプではなくてバイデンが被る。ある意味でバイデンは運が悪い。アメリカ人にしてみれば3年間は良い年だった。
コロナは来たがトランプのとんでもない財政支援政策で、家計も潤ったし、確かに貯蓄率は上がっていった。企業も援助してもらい立ち直る。良いことをやったという印象を与えたのはおそらく間違いない。
バイデン政権でインフレが急騰
連邦銀行が20年3月にコロナでトランプが急激な2兆ドルを超える援助政策をやったときに金融資産をどんどん商業銀行から買い取ることを続けていった。続けたので、その有効需要を金融が支えるという事態もあり、インフレーションが21年のバイデン・ハリス政権になって急激に出た。
連銀もその年の秋ごろ気がつき買い取りを徐々にやめて翌年には全てやめて金利政策に戻る。22年になってアメリカの金利が上がりだした。日本はずっとゼロ金利政策なので日本の円安が展開した。
結局、気がつくのが遅かった。バイデン・ハリス政権は1930年代のルーズベルト大統領が展開したニューディール政策にも匹敵するような公共投資、公共事業計画をやっていたが駄目だった。大々的な財政政策は必要だったが、このバイデン・ハリス政権がやるべきではなかった。
なぜかというとトランプがやってアメリカ経済は急速に回復していって失業率も非常に低くなっていた。アメリカ経済がうまく行き始めたところに追加的にルーズベルト政権以来の大々的な公共投資政策を展開したので金融政策と相まってインフレが深刻になった。
(注1)萩原伸次郎(2023)『資本主義の真実』かもがわ出版
(注2)萩原伸次郎監修、萩原伸次郎、大橋陽、下斗米秀之訳(2024.10.5)『米国経済白書2024』蒼天社出版
質疑応答
森下(座長):質問とかご意見あればお願いします。
(長谷川):アドバイスしているのは大統領諮問委員会なのか。
萩原(講師):アドバイスするのは大統領経済諮問委員会でそんなに力はない。大統領が側近と相談して、誰を委員長にするか選ぶ。大体は大学の教授がなってきた。
アメリカの経済政策は財務長官を中心にして、今はジャネット・イエレンという学者が財務長官でやっているが、間違ったと彼女も言っている。インフレがあんなに激しく展開するとは思わなかった。インフレ対応で後手になったことが問題点。
トランプ政権になって投資ファンドの人が財務長官に就任するということになった。金融緩和という方向で金融優位という政策をトランプの場合には実行していく。
日本には経済政策がないのか
(小平):アメリカの話を聞くと選挙の対立で経済政策が見えている。成長路線というか経済をコントロールする政策が存在している。日本は30年間低成長。それを望んでやったのか分からないが経済政策がない。
(講師):アメリカはシステムを変えない。日本の場合かなり変わった。60年代の古い話であるが、経済は池田にお任せくださいという高度経済成長の牽引主義が展開して大蔵省が経済企画庁とも一体となって経済計画を作って、日本の経済を85年の世界最大の債権国に持ち上げとたところに日本の経済の良さがあった。
経済、アメリカの意向で潰された
ところがそれ以降、アメリカが日本の経済を潰しにかかった。アメリカは産業では勝てない。世界最大の債務国なので85年以降、金融に特化した政策でやっていく。日本がずっと展開してきた「日本型経営指針」と私が言っているやり方を、どんどん潰していった。経済企画庁も今は無いし、経済済財政諮問会議は財界の人が出てくるだけである。昔の自民党の経済政策は、財界だけではなく中小企業とか、農業とか、消費者を展開していた。経済企画庁が経済計画を立てて、通産省が行政指導という形で展開しそれに大蔵省が資金的にどうするかと、政府を軸とする政策が、ある意味うまく展開してきた。日本の高度成長は素晴らしい事態だと思う。それがアメリカの意向でどんどん壊され特に小泉構造改革で、日本のシステムは、経営者が株主とくっついて、労働者が置き去りという事態が続いている。

「アメリカは公文書を保存している。日本はすぐ破棄してしまう。時間が経つと田中角栄問題などが明確になる。アメリカが民主主義を保っているのは公文書の保存」と小平

Make America Great Once Again と言われたが、Make Japan Great と吉池氏
経済一流、政治二流と言われた日本
(吉池):アメリカは政治が主流、政治が国を引っ張っている。
(講師):アメリカは非常に面白い国で。そう簡単に潰れないし、具体的にそこからいろいろなものを展開させていく、非常に興味の尽きない国。アメリカを含めた形で日本がどうするか考えなければ。
(西河):アメリカは、増税と減税に取り組んでいる。日本はみんな増税だからおかしい。選べない。海外に配っている金をゼロにしたら消費税はゼロにできる。そのことをテレビは言わない。GDPが20位ぐらい。昔はアメリカに次ぐ2位。20位なら出さなくても。
(西河):先生からグローバルサウスの話がでたがこの研究会がまさに「地の時代から風の時代へ」ということだ。日本にしろアメリカにしろ、国の借金自体が膨張していって返済できない額にまで来ている。世も末なのかという印象。
(講師):おっしゃる通りアメリカのドルで安穏としている状況ではない。トランプは対中国封じ込め政策という形で強く出ている。流れは無視できない。先進国が途上国と言われた地域の経済を活性化させている。今大きく揺らいできて一体どう展開していくかの状況になっている。安定的な時代でなくて危機的な状況は続く。その中で世界経済がどう安定化するかを考えなければならない時代。
アメリカも衰退している。それに対して中国を中心とする新興諸国が世界経済の中に出てくるが、単純に変わるというのではなく、お互いがお互いを牽制する時代がかなり続く。日本はどうするのかというと、このままではまずいということは皆さんご承知の通りだと思う。それをどうするかも一つ大きな課題になってくる。